「舞姫」森鷗外
・左記の①~⑪と上欄の①~⑪が対応しています。
上欄の番号をクリックするとそこの本文に飛びます。
右の語注の上欄の丸数字をクリックするとその節の語注に飛びます。
①… 一、 帰国の途中、一人船に残り、愁いに沈む
二、 回想記 生い立ちから恋愛の悲劇的結末まで
②… 起 ⅰ生い立ち
③… ⅱドイツ留学の三年間
④… 承 ⅰエリスとの出会い
⑤… ⅱエリスとの恋愛の深まり 免官と母の死
⑥… ⅲエリスとの同棲 通信員の生活
⑦… 転 ⅰエリスの懐妊、相沢との再会
⑧… ⅱロシア行き
⑨… 結 ⅰ帰国の承諾、エリスへの罪悪感
⑩… ⅱエリス裏切りを知り発狂
⑪… 三、 回想記を終えての感慨
この構成は当方で勝手に読み進む目安として設定したものです。
訳文の構成と同一です。
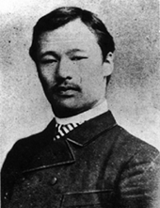 |
| 留学時代の鴎外 資料:鴎外記念本郷図書館 |
以下の原文は「青空文庫作成ファイル」をコピーしたものです。
言うまでもないことですが、原本に丸数字はありません。
① 石炭をば
げに
② 余は幼き
③ 余は
余が
さて官事の
ひと月ふた月と過す程に、おほやけの打合せも済みて、取調も次第に
かくて
余は
官長はもと心のまゝに用ゐるべき器械をこそ作らんとしたりけめ。独立の思想を
彼人々は余が
赤く白く
④ 或る日の夕暮なりしが、余は獣苑を漫歩して、ウンテル、デン、リンデンを過ぎ、我がモンビシユウ街の
今この処を過ぎんとするとき、
彼は
彼は驚きてわが黄なる面を打守りしが、我が真率なる心や色に
「我を救ひ玉へ、君。わが恥なき人とならんを。母はわが彼の言葉に従はねばとて、我を打ちき。父は死にたり。
跡は
「君が
人の見るが厭はしさに、早足に行く少女の跡に附きて、寺の筋向ひなる大戸を入れば、欠け損じたる石の梯あり。これを上ぼりて、四階目に腰を折りて潜るべき程の戸あり。少女は
余は暫し茫然として立ちたりしが、ふと に、
に、 に向ひて斜に下れる
に向ひて斜に下れる
彼は
我が隠しには二三「マルク」の銀貨あれど、それにて足るべくもあらねば、余は時計をはづして机の上に置きぬ。「これにて一時の急を
少女は驚き感ぜしさま見えて、余が
⑤ 嗚呼、何等の悪因ぞ。この恩を謝せんとて、自ら我 下
下
その名を
余とエリスとの交際は、この時までは
嗚呼、
⑥ 公使に約せし日も近づき、我
此時余を助けしは今我同行の一人なる相沢謙吉なり。彼は東京に在りて、既に天方伯の秘書官たりしが、余が免官の官報に出でしを見て、某新聞紙の
社の報酬はいふに足らぬほどなれど、
朝の

 より光を取れる室にて、定りたる
より光を取れる室にて、定りたる
 の
の みたるを、
みたるを、
我学問は
我学問は荒みぬ。されど余は別に一種の見識を長じき。そをいかにといふに、
⑦ 明治廿一年の冬は来にけり。 のつくり]をも揮へ、クロステル街のあたりは
のつくり]をも揮へ、クロステル街のあたりは
今朝は日曜なれば家に在れど、心は楽しからず。エリスは床に
かはゆき独り子を出し遣る母もかくは心を用ゐじ。大臣にまみえもやせんと思へばならん、エリスは病をつとめて起ち、
「これにて見苦しとは
「何、富貴。」余は微笑しつ。「政治社会などに出でんの望みは絶ちしより の下まで来ぬ。余は手袋をはめ、少し汚れたる外套を背に
の下まで来ぬ。余は手袋をはめ、少し汚れたる外套を背に を明け、乱れし髪を
を明け、乱れし髪を
余が車を下りしは「カイゼルホオフ」の入口なり。門者に秘書官相沢が室の番号を問ひて、久しく踏み慣れぬ大理石の
食卓にては彼多く問ひて、我多く答へき。彼が生路は
余が胸臆を開いて物語りし不幸なる閲歴を聞きて、かれは屡 驚きしが、なか/\に余を
驚きしが、なか/\に余を
大洋に
別れて出づれば風 を緊しく鎖して、大いなる陶炉に火を焚きたる「ホテル」の食堂を出でしなれば、薄き外套を透る午後四時の寒さは殊さらに堪へ難く、
を緊しく鎖して、大いなる陶炉に火を焚きたる「ホテル」の食堂を出でしなれば、薄き外套を透る午後四時の寒さは殊さらに堪へ難く、
飜訳は一夜になし果てつ。「カイゼルホオフ」へ通ふことはこれより漸く繁くなりもて行く程に、初めは伯の言葉も用事のみなりしが、後には
⑧ 一月ばかり過ぎて、或る日伯は突然われに向ひて、「余は
此日は飜訳の
鉄路にては遠くもあらぬ旅なれば、用意とてもなし。身に合せて借りたる黒き礼服、新に買求めたるゴタ板の
魯国行につきては、何事をか叙すべき。わが
この間余はエリスを忘れざりき、否、彼は日毎に
又程経てのふみは頗る思ひせまりて書きたる如くなりき。文をば否といふ字にて起したり。否、君を思ふ心の深き
嗚呼、余は此書を見て始めて我地位を明視し得たり。恥かしきはわが
大臣は既に我に厚し。されどわが近眼は唯だおのれが尽したる職分をのみ見き。余はこれに未来の望を繋ぐことには、神も知るらむ、絶えて
⑨ 嗚呼、独逸に来し初に、自ら我本領を悟りきと思ひて、また器械的人物とはならじと誓ひしが、こは足を縛して放たれし鳥の暫し羽を動かして自由を得たりと誇りしにはあらずや。足の糸は解くに由なし。
我心はこの時までも定まらず、故郷を
「幾階か持ちて行くべき。」と
戸の外に出迎へしエリスが母に、馭丁を
エリスは
二三日の間は大臣をも、たびの疲れやおはさんとて
黒がねの
足の運びの 我は
我は
四階の屋根裏には、エリスはまだ
驚きしも
余は答へんとすれど声出でず、膝の
⑩ 人事を知る程になりしは
後に聞けば彼は相沢に逢ひしとき、余が相沢に与へし約束を聞き、またかの夕べ大臣に聞え上げし一諾を知り、
これよりは騒ぐことはなけれど、精神の作用は
余が病は全く癒えぬ。エリスが生ける
⑪ 嗚呼、相沢謙吉が如き良友は世にまた得がたかるべし。されど我
(明治二十三年一月)
このサイトの本体=
底本:「現代日本文學大系 7」筑摩書房
1969(昭和44)年8月25日初版第1刷発行
1985(昭和60)年11月10日初版第15刷発行
入力:多羅尾伴内
校正:蒋龍
2004年6月29日作成
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
●表記について
このファイルは W3C 勧告 XHTML1.1 にそった形式で作成されています。 [#…]は、入力者による注を表す記号です。 「くの字点」は「/\」で、「濁点付きくの字点」は「/″\」で表しました。 「くの字点」をのぞくJIS X 0213にある文字は、画像化して埋め込みました。 この作品には、JIS X 0213にない、以下の文字が用いられています。(数字は、底本中の出現「ページ-行」数。)これらの文字は本文内では「※[#…]」の形で示しました。
「金+
 のつくり」161-下-29
のつくり」161-下-29